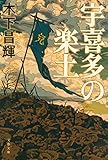宇喜多秀家(うきたひでいえ)
戦国大名[日本]
(明暦元年11月20日没)
1655年 12月17日 死去享年84歳

宇喜多 秀家(うきた ひでいえ)は、安土桃山時代の武将・大名。
宇喜多氏の当主。
通称は八郎、参議に任じられた天正15年以降は備前宰相と呼ばれた。
父・直家の代に下克上で戦国大名となった宇喜多氏における、大名としての最後の当主である。
豊臣政権下(末期)の五大老の一人で、家督を継いだ幼少時から終始、秀吉に重用されており、秀吉の養女・豪姫を妻として豊臣一門としての扱いを受けていた。
関ヶ原の戦いで西軍の主力の一人として敗れて領国を失うまで、備前岡山城主として備前・美作・備中半国・播磨3郡の57万4,000石を領していた。
名称=
「宇喜多秀家」はあくまでも歴史用語である。
天正10年(1582年)の元服時には仮名として「八郎」、諱(実名)として「秀家」を名乗り、宇喜多家の家督を継承したが、宇喜多の名字が使われた記録は無い。
また、宇喜多氏の本姓は三宅氏とされているが、三宅姓が使われた記録も発見されていない。
唯一の例外として、慶長2年(1597年)11月と翌年9月に執筆された備中吉備津社の棟札が知られていたが、いずれも秀家は領国不在の折で、父・直家の代から崇敬されていた遍照院の円智による代作であったことが判明している。
天正13年の書状では「羽柴八郎」となっているが、その前年には後見人の羽柴秀吉から名字を省略されて「八郎殿」と称されており、名字の省略は大抵は同名だったことから既に「羽柴八郎」を称していた可能性が高 ……
宇喜多秀家が亡くなってから、370年と60日が経過しました。(135203日)