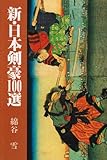大石種次(おおいしたねつぐ)
剣客、筑後国柳河藩士[日本]
(大石神影流 創始者、文久3年11月19日没)
1863年 12月29日 死去享年67歳
大石 種次(おおいし たねつぐ)は、江戸時代後期から幕末の剣客、柳河藩士。
諱は種次。
通称は進、のち七太夫と改名。
隠居号は武楽。
大石神影流の創始者で、男谷信友、島田虎之助と並ぶ「天保の三剣豪」の一人。
7尺といわれる長身に加え、5尺3寸の長竹刀を使用しての左片手突きは強烈で天下無双の技ともいわれた。
六組での所属は立花壱岐組。
家格は給人。
生涯=
大石神影流の創始=
柳河藩士・大石種行(太郎兵衛)の長男として、筑後国三池郡宮部村(現在の福岡県大牟田市大字宮部)に生まれる。
種次は4、5歳のころから祖父の種芳に大石家が師範として担当する剣術新陰流(または愛州影流)派及び大島流槍術剣槍術を学んだという。
父種行は柳河藩の剣槍術師範役に加え、柳河藩支藩三池藩の師範役も兼ねていた。
このため交際費がかさみ、家禄30石では苦しい生活を強いられた。
種次は幼時から馬を飼い、門前の田畑を耕して家計を補ったという。
しかし、そのためか、ある年、正月恒例の御前試合に思わぬ惨敗を喫した。
種次はこれに発奮して、石をつるして突き技を稽古、胴切りと諸手突き、さらには生来の左利きを利用して独自の左片手突きを案出した。
従来の唐竹面、長籠手、袋竹刀の防具に代えて、13本穂の鉄面、竹腹巻、半小手を使用するようにしたという。
このとき種次18歳で、これより大石新影流を称した。
九州武者修行=
文政5年(1822年)、神陰 ……
大石種次が亡くなってから、162年と54日が経過しました。(59225日)