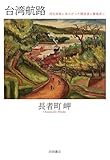藤島武二(ふじしまたけじ)
洋画家[日本]
1943年 3月19日 死去脳溢血享年77歳

藤島 武二(ふじしま たけじ、1867年10月15日(慶応3年9月18日) - 1943年(昭和18年)3月19日)は、明治末から昭和期にかけて活躍した洋画家である。
明治から昭和前半まで、日本の洋画壇において長らく指導的役割を果たしてきた重鎮でもある。
ロマン主義的な作風の作品を多く残している。
生涯=
薩摩国鹿児島城下池之上町(現在の鹿児島県鹿児島市池之上町)生まれ。
鹿児島藩士の三男。
父の病没(1875年)と、西南戦争での長兄・次兄の戦死(1877年)により、11歳で家督を継ぎ、専ら母の手で育てられた。
幼い頃から画才を認められる。
母方の先祖が狩野派の島津家抱絵師であったとも言われている。
1882年(明治15年)に、小学校を卒業して、後の中学造士館である鹿児島中学に入学。
この頃、四条派の画家平山東岳について正式に日本画を学び始める。
1884年(明治17年)に洋画修行を志して上京するが、1885年(明治18年)一時帰郷した後に再び上京して、日本画の四条派川端玉章に師事。
洋画を志してはいたが、当時工部美術学校も廃校となっていて、フェノロサらの唱道により日本画勃興のタイミングだったこともあり、先輩や親戚から洋画を学ぶ前にまず日本画を学ぶことが得策だと説かれたため、川端玉章の門に入り1890年(明治23年)まで日本画を学んだ。
玉章門下時代の号は玉堂で、日本美術協会に作品を2回出品し、受賞したこともあった。
また、1886年(明治19年)の20歳の時か ……
藤島武二が亡くなってから、82年と245日が経過しました。(30196日)